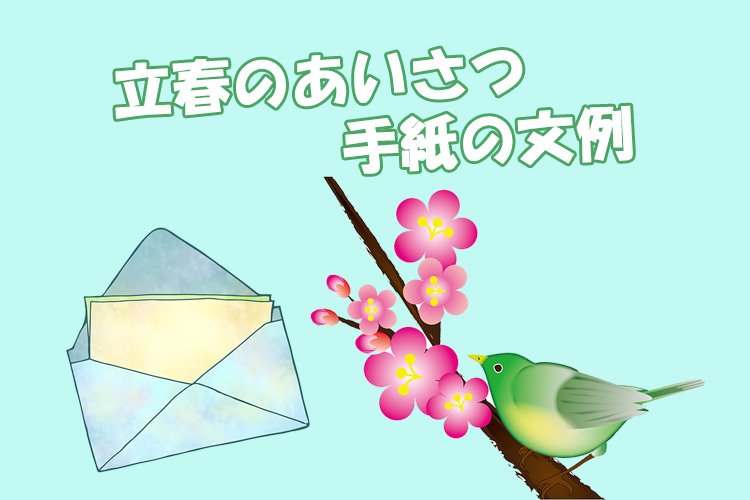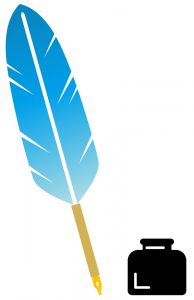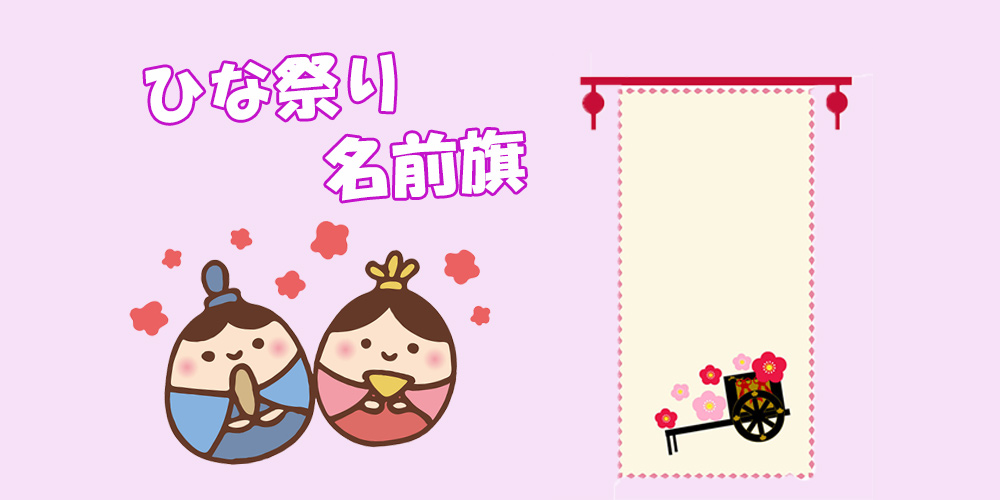こんにちは、ぽんたろうです!
近年では、メールやSNSでのやりとりが多くなり、季節毎に手紙を出す習慣は少なくなりました。
でもやっぱり、手書きでいただく手紙はとても嬉しいもの。
今回は、立春に出す手紙の書き方のポイントを調査してまとめました。
ぜひお役に立てて下さいね!
立春の挨拶の書き出し文例
立春を迎えると、春の始めとされています。
この頃に出す手紙では、手紙が相手に届く日を考慮しなければなりません。
立春よりも前に届く手紙なら、立春への期待が篭った書き出しにするように気をつけましょう。
立春に届く手紙では、春に向けた期待の言葉や「春になってもなお寒いですね」という意味を込めた書き出しをするのが良いでしょう。
また、ビジネス文章では時候の挨拶を用いて書き始めるのが一般的です。
ここでは、立春の手紙の書き出し例を上げていきます。
・余寒の厳しい毎日が続いております
・立春が過ぎ、初の訪れが待たれる頃となりました
・梅香る季節となりました
・梅の蕾もようやくふくらみ始め
・遠山の雪の色も和らぎ
・冬の名残もまだ去りやらぬ頃
・ひと雨ごとに暖かく
・草の芽も萌え
・いくらか寒さも緩み
・春浅く風も未だ冷たく
・雪解けの雫にも春の近づく足音が聞かれ
・鷹の初音も爽やかに
・寒さなお厳しき
・日に日に暖かさを増してまいりました
・春の日差しが待ち遠しい今日この頃
[getpost id=”1948″ target=”_blank”]
立春の挨拶の結びの文例
はじめに記載した季節の挨拶を頭語と言い、この頭語には必ず結語が必要になります。
一般的によく知られているものでいうと、「拝啓」と始めた場合には「敬具」で終わるというものがあります。
立春の手紙にも、結びに適した文章がありますので、紹介していきます。
・もうまもなく春の訪れ
・春とはいえまだまだ寒い二月
・日脚は伸びてもまだしばらくは寒さが続きますが
・残雪の寒さが身にしみますが
・二月は朝夕の寒さごとに厳しい時
・余寒厳しき折
・余寒なお去り難き折
・皆様が良き春を迎えられますよう
・梅の香る季節です
・春近しとはいえ、寒さはまだまだ厳しい今日この頃
・立春を過ぎ、春を待ちわびるこの頃
季節の挨拶は不要です。
「取り急ぎお知らせまで」
「まずはご連絡まで」
など一言添えて結びとなります。
[dgad]
立春の手紙に使う季語
四季がある日本には、昔から季節を表す独特な表現がたくさんあります。
また、二月の季語だからといって二月ならいつでも使えるものでもありません。
同じ月でも上旬・中旬・下旬によっても使用するものが異なります。
それに気をつけて手紙に書く季語を選んでいきましょう。
下記に二月の季語と、手紙を送る時期に最適な季語をそれぞれご紹介します。
・春寒の候
・晩春の候
・残雪の候
・解氷の候
・厳寒の候
・向春の候
・節分の候
・春浅の候
・軽暖の候
・梅花の候
・晩冬の候
・立春の候
・晩冬の候
・立春の候
・余寒の候
・梅花の候
・春寒の候
・向春の候
立春に使用する最も適切な季語は上旬にある季語であり、手紙を出す時期が立春よりも遅れてしまう場合には中旬からの季語にするのが最適です。
ここでは「候」を使用していますが、場合によっては「みぎり」とすることもありますよ。
相手から送られてきたものが「みぎり」であっても間違いではありません。
聞き慣れない方にとっては少し違和感を感じてしまうこともあると思いますが、これも正式な季語の一つです。
「候(こう)」というのは「〜と季節も移り変わってきましたが」という意味を持っています。
「みぎり」というのは昔女性が書く手紙に多く使われていたもので、候よりも柔らかい意味合いで使用することができます。
「折」なども似たような意味合いで使用されます。
そのため、ビジネス文章で使用するのであれば「候」が適しており、一般的かもしれません。
まとめ
いかかでしょうか?
きちんとした手紙を書くには、やはりそれなりのルールがあるものです。
でも、これらの約束事が守られた手紙は、送り主のあなたに対する印象をアップしてくれるでしょう!