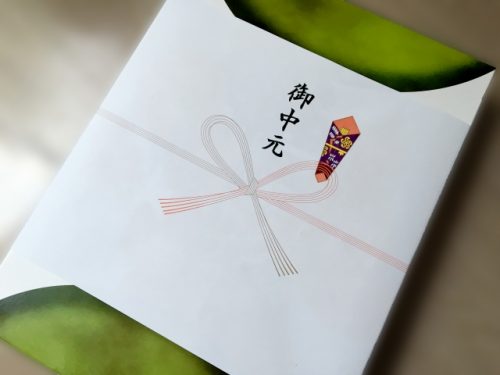現代だと、暑気払いと称して夏場にビアガーデンで飲み会というシーンを思い浮かべるでしょうか。
でも、暑気払いというのは単に夏場の宴会のことではなく、きちんとした意味と実施の時期があったのです。
暑気払いの由来や時期を踏まえたうえで飲み会に参加すれば、ちょっとした話のネタにもなりますよ。
暑気払いの意味とは?
暑気払いとは、本来「暑さをうち払う」という意味で使われます。
具体的には、暑さを打ち払うために、冷たい食べ物や体を冷やす効果のある食べ物や飲み物、または体を冷やす効能のあるとされる薬や漢方などで、体内に溜まった熱気を取り除こうとすることです。
昔の暑気払いとは、漢方の効能を中心に考えられていたようです。
現在では、漢方の効能に期待することはほとんどなくなり、夏の暑さと日ごろの仕事の慰労を兼ねて、宴会を実施する習慣になったようです。
暑気払いの時期はいつ頃?
では、暑気払いとはいつ頃行うのが適切なのでしょうか。
一般的には、二十四節気の夏至から処暑のあいだに行うようです。
夏至は一年で最も昼が長い日で、6月の20日頃です。
しかし、このくらいの季節は梅雨が明けていない地域もあり、実際に夏至過ぎに暑気払いを実施するのは少々早めかもしれません。
処暑はお盆を過ぎた8月23日頃、「夏の暑さが止む」といわれています。
夏の暑さを打ち払うのが元来の目的ですから、遅くても処暑までに実施したほうが良いですね。
ですので、冷たい飲み物を美味しくいただくのであれば、梅雨明けからお盆過ぎくらいがベストのようです。
暑気払いの服装などの注意点は?
自分だけ浮いたり目立ったりはイヤだなという場合は、暑気払いを実施する幹事さんや、一緒に参加する友人や同僚に確認しておくのが無難だと思います。
通常の飲み会とは分けて、あえて「暑気払い」と形式のある会であれば、オフィスカジュアルをボーダーラインとした、少し改まった格好がおススメです。
「場をわきまえているな」と上司のウケが良かったりするかもしれませんよ。
暑気払いの乾杯の挨拶例
みなさんもご経験があるかと思います。
目の前にビールが待っているのに、長い挨拶で飲むに飲めないというパターンです。
しかし「乾杯!」の一言では唐突すぎますので、乾杯の前に一言添えましょう。
[su_note note_color=”#66ddff”]
「僭越ながら、乾杯の音頭を取らせていただきます。」の後に
・この会で、飲んで食べて、暑さを乗り切りましょう!乾杯!
・暑さを乗り切るべく、みなさんで今日は食べて飲んで、盛り上がりましょう、乾杯!
・今日は大いに飲んで食べて、暑気払いといきましょう、乾杯!
[/su_note]
などです。
もちろん乾杯の前に、全員にグラスが渡っているかを確認してから挨拶をお願いしますね。
暑気払いの締めの挨拶例
締めの挨拶も短く簡潔に行います。
会も後半になると、お酒の量も増えてきており、最後の挨拶は何を言っても記憶にあまり残りません。
また、締めのタイミングはあらかじめ会の最初に打ち合わせしておきましょう。
後半はだらだらムードになりがちなので、暑気払いの締めは時間でピタッと区切って行ったほうが良いと思います。
締めの挨拶は文言よりも声の音量と明瞭さが必要です。
そのため、挨拶を任されたら締められるくらいの酒量にとどめておきましょう。
文言としては1~2文が適切です。
[su_note note_color=”#66ddff”]
「宴もたけなわかと思いますが、一度ここで締めさせていただきます」の後に
・暑さが続きますが、みなさん乗り越えていきましょう!
・みなさん暑気払いして、暑さも乗り越えられそうですね!
・最後に、当社の繁栄を願って1本締めとさせていただきます。お手を拝借
※1本締めするか否かは、社風などもあるかと思いますので、事前に確認しましょう。
[/su_note]
まとめ
ここまで、暑気払いの意味や時期をまとめてきました。
暑気払いは日本の四季が生んだ文化なのでしょうね。
中身は単なる飲み会でも、暑気払いという名の付く以上はしっかりと暑さに打ち勝てるよう、活気のある宴会にしたいものですね!